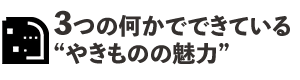はじめに
株式会社大築窯炉工業は、単なる焼成炉の製造企業ではありません。
平成8年の特許取得から始まり、創業の理念とともに積み上げられた歴史は、職人たちの情熱と努力の結晶です。創業以来、全国の陶芸家やユーザーとの信頼の絆を深めながら、常に技術革新と伝統の継承に取り組んできました。
本記事では、そんな大築窯炉工業の歩みと、その背後にある熱い想い――時代を超えて進化し続ける技術と、人々の心を動かす伝統の物語――を紐解いていきます。
大築窯炉工業の物語は、一人の陶芸家であり創業者、谷口俊夫から始まります。彼はもともと製陶業を営んでいましたが、時代の変動や協力会社の廃業など、数々の逆風に直面し、製陶工場を閉ざさざるを得ませんでした。そんな中、個人陶芸家として新たな道を歩んだ俊夫は、ある日、自身の作風をより自由に表現できる窯の必要性を痛感します。
そのとき、彼はかねてからの夢を実現するため、陶芸家としての友人と手を取り合い、試作機としての第1号ガス窯を作り上げました。このガス窯は、ガスでの焼成が終了した後に薪を投入することで、薪窯特有の風合いが表現できるという、今までにない革新的なものでした。焼成データを友人と共有しながら、笠間でもこの新しい窯作りが語られると、やがて注文が殺到するほどの注目を浴びたのです。
その頃、日本はバブル経済の崩壊後、陶芸界でも新たな作風を模索する時期にありました。私は20代半ばで、将来に対する不安と可能性の狭間で揺れていた時期でした。そんな私にとって、父の姿―忙しくも誇り高く働く姿―は、いつしか「自分も窯づくりに挑戦してみたい」という強い衝動を呼び起こす原動力となりました。
父が考案した新しい機能をもった窯。それは、単なる製品ではなく、父の想いと時代を見据えた革新の象徴でした。父の夢を受け継ぐため、私は信頼できる弁理士を探し、必要な文章を整えて特許庁に提出しました。当時、特許審査には7年から10年の長い道のりが待っていました。一つひとつの審査を経て、遂に8年後の春に特許が下りたそのとき、私にとっては希望の光と同時に、耐えがたい悲報が訪れました。その年の夏、父は癌と闘いながらも、特許取得という夢と引き換えに、静かに息を引き取りました。
特許取得に、私は父の挑戦を絶対に無駄にしないという意味や、仕事を継続する意義を見出していました。だからこそ、父の他界は心に大きな穴を開け、ショックから立ち直るまでに多くの時間が必要でした。しかし、父の情熱と革新の精神は、私たちが今日まで歩んできた道そのものです。
伝統と革新への挑戦
父が他界してしばらくの間、私たちは製品の品質維持や注文への対応に必死でした。
これまで父が背中を見せてくれた安心感が急になくなり、製作の最中に小さな不安が大きく感じられる日々が続きました。頼り切っていた父の存在が、今は私自身にのしかかる重みとして現れ、仕事に対する自信も揺らいだのです。
そんな中、ひとつのひらめきが私を救いました。
過去に父の時代からお付き合いのあるガス窯ユーザーへの感謝と信頼を形にするため、「ニュースレター・窯ナビ」を発行することにしたのです。
窯ナビでは、父の時代にご購入いただいたお客様のインタビューや、新たに信頼してくださったユーザーの作陶への熱い思いを掲載しました。
これにより、ユーザー同士の絆が深まるだけでなく、私自身も「自分の作る製品には価値がある」と再び自信を取り戻すことができました。
職人たちの情熱と技の伝承
窯ナビの発行と並行して、私が次に取り組んだのは、ガス窯のさらなる性能向上でした。
父が友人と共に試作機をつくり上げたあの頃と同じように、私も自分のアイデアを形にすべく、新たな試作窯づくりに挑戦しました。その一環として応募したのが、「ものづくり補助金」です。
採択された後は、試作と改良を重ねる中で、つくばの産業技術総合研究所や茨城県工業技術センター(現・工業技術イノベーションセンター)や笠間陶芸大学校の専門家から貴重な助言をいただきました。
それらを反映させることで、自社のガス窯は従来以上に高性能かつ使いやすい製品へと進化し、非常に満足のいく成果を得ることができました。
この取り組みは高く評価され、ものづくり補助金の採択企業924社の中から、特色ある20社のひとつに選ばれ、「成果事例集」にインタビュー記事として掲載されました。
さらに、次なる挑戦として応募した「いばらきデザインセレクション2019」では、陶芸窯としては珍しく、「選定」という名誉をいただきました。これは、当社のガス窯が単なる工業製品ではなく、作陶家に寄り添う「使いやすさと仕様」のデザインが評価された結果です。
お客様との絆と未来への展望
補助金を活用して製品をブラッシュアップする中で、ユーザーの声は大きな支えとなりました。
窯ナビで取り上げたインタビュー記事は、多くの作陶家から好意的な反応を得て、製品への信頼を再確認する貴重な機会となりました。
自社製ガス窯を手にしていただいたユーザーたちの、作陶に向けた情熱や希望の声は、私たちが次の一歩を踏み出す原動力です。
私自身、これからもユーザーの夢を支え続けるべく、製品開発とサービス向上に努め、時代のニーズに応えていきたいと考えています。
地域社会と社会全体への貢献
私たちの取り組みは、単なるガス窯の技術革新にとどまらず、陶芸作品の品質向上や事故防止、エネルギーの有効活用といった多角的な面で、地域社会や社会全体に貢献するものです。
まず、ガス窯焼成のノウハウを確立することにより、1回の焼成での仕損じ品を減らし、本来の作陶家の想い通りの作品を再現する取り組みを進めています。
やきものは「一焼、二土、三細工」と言われるように、最も重要な工程である「焼き」について、まだ十分な情報共有がなされていないという課題があります。私たちは、焼成理論と実践知を融合し、ユーザーに分かりやすく伝えることで、より良い作陶環境づくりに貢献したいと考えています。
また、LPガスの特性を正しく理解することで、ガス窯をより安全に使うことができるという知識も広めています。
事故防止はユーザーの安心につながるだけでなく、ガス窯全体の信頼性を高め、ひいては窯業界全体の発展にも寄与します。
エネルギーの有効活用もまた、社会的責任のひとつです。
1回の焼成で多くのA級品が得られれば、エネルギー効率が上がり、無駄な焼成回数を減らすことができます。
作品ごとに適した焼成温度や炉内雰囲気を的確に作ることで、笠間のように多様な作風が混在する産地においても、個々の作家の創造性を尊重しつつ、エネルギーを無駄にしないものづくりが可能になります。
さらに、まだ使える窯が廃棄されると、大量の耐火物が産業廃棄物として環境に負荷をかけてしまいます。私たちは、それらを可能な限り修理・再生することで、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の視点から廃棄物の削減に取り組んでいます。再生可能な資源としての窯に、再び命を吹き込むことは、ものづくりの責任としても、環境保全への具体的な行動としても重要だと考えています。
参考:新聞記事「笠間焼が育てたガス窯技術」朝日新聞2020.1.30