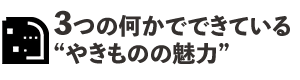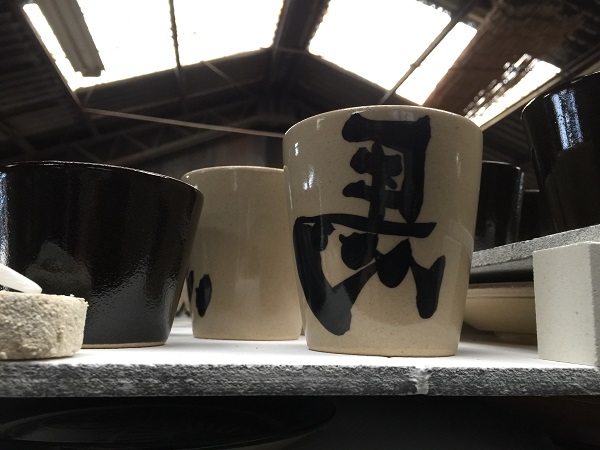先日、福島県の公共施設に設置されているガス窯の点検業務を依頼され、出張してきました。
名板を見てみると、もう21年も経過していて驚きました。
納入当時のことは何となく覚えていたのですが、改めて再訪すると「よくこんな場所に設置したものだなあ」と感心することがあります。
現地には、ガス窯を使っている高齢の方々が5~6人ほど集まっておられ、とても熱心に話を聞いてくださいました。
公共施設のガス窯でよくあるのですが、「メーカーの人が来るなら質問したい」という方が多く、今回も同じように次々と質問をいただいたんです。中でも印象的だったのが、「点火当初、窯の中の湿気を早く抜きたいからバーナー上の色見穴のフタを開けておく」というお話でした。
陶芸雑誌などで「湿気は早く抜くべき」と書いてあることがあるためか、実際にそうしている方も多いようです。
そこで今回は「湿度乾燥」と「過熱水蒸気乾燥」についてのお話です。
湿度乾燥と過熱水蒸気乾燥のポイント
1.乾燥速度の違いによる収縮の不均一を防ぐ
陶芸作品は厚みや形状によって乾燥速度が異なり、薄い部分が先に収縮して厚い部分とのタイミングがずれると、亀裂(クラック)が生じやすくなります。また、厚い部分に残った水分が急激に沸騰すると「水蒸気爆発」を起こし、作品を粉々に破壊する恐れもあります。そこで必要なのが、窯内に適度な湿気を保ちながら、ゆるやかに温度を上げることです。
2.過熱水蒸気乾燥の理論を活用する
工業的な乾燥技術である「過熱水蒸気乾燥」では、沸点以上に加熱した水蒸気を材料に当てることで、材料の温度を沸点付近に安定させつつ、効率よく内部の水分を蒸発させます。陶芸における湿度乾燥と似ているのは、「素材を一気に乾かすのではなく、水蒸気を利用して安全に、かつ均一に乾燥させる」という点です。
3.180℃前後をあえてゆっくり通過する意義
過熱水蒸気乾燥の考え方を焼成に取り入れるなら、180℃前後をある程度キープするのがポイントです。220~250℃付近で起こりがちな水蒸気爆発を防ぐためにも、この温度帯を一気に通過せず、内部の水分がじわじわ移動・排出できる時間を確保します。
具体的なプロセスの一例
- 点火後の低温域(~180℃)
- ガス圧を低めにし、ダンパーもやや閉じて炉圧を持たせた状態で窯内の湿度を保つ。
- 作品や窯道具、窯本体がゆっくりと温まり、器物の表面と内部の温度差が大きくならないようにする。
- 180~220℃付近での滞留
- 急いで温度を上げず、このゾーンである程度時間をかける。
- 湿度が高いほど、内部の水分が表面へ移動しやすく、乾燥の不均一を抑えられる。
- 220~250℃を慎重に通過
- 水蒸気爆発が起こりやすい危険領域。急激な温度上昇を避ける。
- 300℃までの焙りを完了
- 大西政太郎氏の言う「焙り」の終わりにあたる温度帯。ここまで来ると作品の大半の水分は抜けていますが、肉厚の作品は依然注意が必要。
4.「湿気を早く抜く必要はほとんどない」理由
先日の福島での事例のように、点火当初から色見穴のフタを開けっぱなしにして湿気を抜こうとする方もおられます。しかし、低温域で湿度を抜きすぎると、表面だけが先に乾燥して収縮し、内部の水分とのズレが生じる可能性が高まります。むしろ、ある程度湿度が残っていたほうが作品全体がゆるやかに乾き、トラブルを回避しやすいのです。
まとめ
窯の点検業務や使用指導の現場では、「湿度はなるべく早く飛ばしたほうがいい」という意見を耳にすることがありますが、実際には急激な乾燥こそが亀裂や水蒸気爆発の原因になります。過熱水蒸気乾燥の理論が示すように、適度な湿気とゆっくりとした温度上昇が、厚みや形状の異なる作品を安全に乾燥させるカギなのです。
今回の福島出張でのやりとりをきっかけに、改めて「湿度乾燥」の意義を再確認できました。皆さんもぜひ、素焼きの段階では湿度を上手に味方につけてみてください。180℃前後で時間をかけることが、220~250℃の危険領域を安全に乗り越えるためのポイントになります。結果的に、亀裂や爆発のリスクを大幅に下げながら、完成度の高いやきものに仕上げられるでしょう。
参考文献 『陶芸の土と窯焼き』大西政太郎著 『初歩から学ぶ乾燥技術』中村正秋、立元雄治著
『窯業操作』社団法人窯業協会